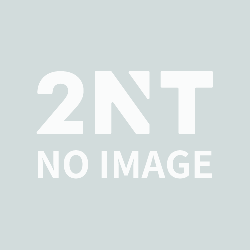ヘッドライン
ヘッドライン
カテゴリー [ 出版・書店関連 ]
Amazon売り切れ、“難民”発生。でも重版なし――“余ってる”のに品薄になるマンガの流通ジレンマ
1 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[] 投稿日:2012/09/09(日) 04:41:29.45 ID:???
今回は『マンガのレビュー・情報サイト ネルヤ』さんからご寄稿いただきました。
■Amazon売り切れ、“難民”発生。でも重版なし――“余ってる”のに品薄になる
マンガの流通ジレンマ
マンガや書籍は店頭にない場合、書店から注文することができる。これは昔からある
方法なので利用したことがある人も多いだろうが、ご存知のとおりすべての作品が必ず
手に入るわけではない。
22日、こうしたマンガの流通と在庫をめぐる問題がTwitterの書店員やマンガクラスタの
間で話題になった。
■TLで話題に上がった「市中在庫」とは何か?
書店で注文しても入荷できないというとき、いくつかのパターンが考えられる。代表的な
のは、いわゆる「絶版(=品切れ重版未定)」。出版社にもすでに在庫がなく、かと
いって重版する(新たに作品を作る)予定もないので手に入らないというケースだ。
だが、商品はあるのに手に入らないということもある。たとえば、「市中在庫」が多すぎ
る場合だ。
「市中在庫」というのは、書店にある在庫のこと。日本の場合、一般的に本が店頭に並ぶ
とき、出版社から委託販売されている形になり、売れなかった場合は(さまざまなルール
はあるが)原則として出版社に返品できる。つまり、出版社から見れば、店頭に並んで
いる作品でも、売れていなければ在庫と同じなのだ。
そのため、一部の書店で売り切れていても、大型書店などに大量に単行本が残っている
(市中在庫が多い)場合、注文が入っても重版を行わず、書店からの返本を待って再配本
というケースは実際多い。だが、その結果、読者が読みたいときに作品が届かないことは
起きてしまう。
また、TLでは「出版社にはあるが、取次(本の流通業者)に在庫がないというパターン」
も挙げられていた。出版社は印刷した本を、すべてひとつの取次に渡しているわけでは
ない。複数ある取次サイドはそれぞれに預かる本の数を決めており、ある取次には在庫が
あって、別の取次には在庫がないということもありうる。また、出版社に在庫があっても
、取次が持っていないこともある。
書店は取次だけでなく、出版社に直接注文をすることももちろんできる。だが、出版社に
よって追加注文のシステムもさまざまで煩雑であるため、書店によっては取次とのみ
やりとりをしている店舗もあるようだ。こういった店舗の場合、出版社に在庫があっても
「入荷なし」となる場合があるだろう。
ソース:ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/248066
(つづく)
2 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[sage] 投稿日:2012/09/09(日) 04:42:25.07 ID:???
>>1のつづき
■Amazonでは売り切れ、でも実売は……
こうした流通のミスマッチ問題は、しばしば話題になることがあり、場合によっては
流通システムや出版社、取次への批判に直結することも多い。「取次の配本がバカだから
」「出版社がいつまでも重版しないから」といった論だ。
こうした批判はある面では間違ってはいない。出版社は読んで欲しいと思っており、
読者は読みたいと思っているのに、商品が届かない。これは小売業にとってもっとも
不幸な状態であり、本来であれば絶対に避けたいことだ。
出版社や取次は基本的に「見つからない!」という声に対して謝るしかない。だから、
いっそう読者や作家からすれば怠慢に見えてしまう。だが、彼ら自身も届けられない
ジレンマに苦しんでいる。
たとえば、市中在庫の問題。出版社の人間に聞くと、こんなケースがよく起こっているという。
100冊の本があったとして、それを大型書店に50冊、中小規模書店に2冊ずつ合計25店舗に
分配。結果、大型店では50冊中20冊、半数の小規模店で売り切れ、残り12店舗で各1冊売れた。
これは一見悪くない数字だ。売り切れている店舗も多いので、そのエリアの読者は「
足りない」と感じるし、書店からの追加注文も入る可能性は高い。しかし、計算してみる
と、実売率は「20+26+12」でわずか58%。4割以上が“余っている”状態だ。
発売直後の動きならともかく、ある程度の期間をかけてこの数字なら、出版社としては
重版できないのが実情だという。もちろん、リスクを冒して重版することで、店頭で
火が付き、ヒットにつながる可能性もあるだろう。だが、ますます在庫が増え、重版する
ことで赤字になっていく可能性の方が高い。かといって、市中在庫がすぐ返ってくるわけ
でもないので、エリアによっては品薄感が続くし、中小書店の売りたいのに売れないと
いう不満も高まる。出版社にとって返本はイヤなものだが、市中在庫が偏っているとき
などは「むしろ返本してほしい」と思っていることもあるようだ。
これはAmazonなどでも同じ。「Amazonで売り切れが続いている」という場合も、実は
実売30%程度なんてこともあり得るという。毛細血管のように張り巡らされた書籍の
流通は、一部だけ見てもそれが全体像と一致するとは限らないわけだ。
さらに、意外と論点として挙げられないが、返品、再配本のコストもバカにならないと
いう。再流通させるコストだけでなく、「改装費」もある。何度も店頭に並び、流通を
繰り返せば新品の本も傷んでくる。これをキレイにし、カバーを掛け替えたりするのが
本の改装。ケースバイケースだが、こうした再配本を3回も行うと利益がなくなるという
出版社もあるという。
(つづく)
3 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[sage] 投稿日:2012/09/09(日) 04:43:19.36 ID:???
>>2のつづき
■商品であり、販促ツールでもある本
なら、もっと均等に近くなるように配ればいいとも思えるが、なかなかそうもいかない。
本という商品は、たぶんちょっと特殊なものだからだ。
たとえば、洗剤やお菓子であれば、店頭以外のメディアで大々的な広告を打つモデルが
一般的だ。が、刊行点数(商品の種類)が多い出版では、そういうモデルはほとんど
なく、多くの人が店頭でその存在を知る。つまり、本は商品であると同時に、それ自体が
販促物に近い側面も持っているのだ。
均等に近い配本にして、数冊程度ずつ入荷しても、書店で大きなスペースは確保できない
。1冊や2冊だと、最初から棚刺し(表紙を見せるように置く平積みでなく、本棚にささっ
て背表紙しか見えない状態)になってしまい、ほとんど目に止まらない状態になる。
こうなると1冊入って1冊残るというパターンが多くなる。その店舗では実売0%だ。2冊
入った書店で1冊売れても50%、3冊入って2冊売れてようやく60%オーバー。
一般に本を全国の書店に行き渡らせるには1万部前後必要になるといわれている。最初
から数十万部、数百万部と印刷されるヒット作はいいが、多くの作品はそんなに刷られる
ことはない。少部数の作品になれば、初版数千部というのもザラだ。そもそもすべての
書店に1冊ずつ配ることもできないわけだ。この状態で少部数ずつ配本するのはむしろ
自殺行為に近い。結果、一部の書店に本が集中し、「あるのに手に入らない」市中在庫
問題が起こったりする。
■“難民”になったらどうすればいい?
では、我々読者がきちんと欲しい作品にリーチするにはどうすればいいだろう?
流通システムの改善というのはもちろん課題としてあり、たとえばどこに何冊あるかが
いつでもわかるデータベースを作るというような案が出されることがある。が、現実問題
として街の本屋さんから大手チェーンまでを横断するシステムを一括で導入するのは、
なかなか難しい部分がある。配本数の最適化も何十年と試行錯誤を繰り返しながら進んで
きたのが今の状態で、今後も少しずつ変わっていくしかないだろう。
読者ができることとして一番確実な方法のひとつは予約だ。欲しい本は事前に書店で
予約して、確保しておく。
とはいえ、いつどんな作品が出るかを詳しく把握している人はそう多くないだろう。
発売日以後であれば、書店の在庫検索を使うのも手っ取り早い。ジュンク堂や紀伊國屋
書店など、オンラインである程度の在庫状況を知ることができる書店もある。
近隣にそういった書店がない場合は、e-hon*1を使う手もある。これは取次のトーハンが
運営しているサイトで、注文すると近くの書店に本が届き、受け取ることができるという
もので、いわば、書店での注文を自分でできるサービスだ。在庫さえあれば2日以内に
出荷され、書店で受け取るなら配送料もゼロ。利用している書店で注文ができないときは
、こちらで在庫を探してみるのも手だ。
(つづく)
4 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[sage] 投稿日:2012/09/09(日) 04:44:10.18 ID:???
>>3のつづき
*1:e-hon
http://www.e-hon.ne.jp/bec/EB/Top
マンガ、書籍の流通は複雑で難しく、著者、出版社、取次、読者などの間で批判や対立が
起こることも多い。仕組みの抱えるジレンマを理解することで、全体が協力して改善に
向かうこともできるのではないだろうか。
【08/23追記】
取次が運営しているサイトとして、ほかに日販のHonyaClub*2というサイトがあるという
情報をいただきました。
直販、書店への取り寄せ、 在庫確認などができるようですので、参考までに追記させて
いただきます。
*2:HonyaClub
http://www.honyaclub.com/shop/default.aspx
執筆: この記事は『マンガのレビュー・情報サイト ネルヤ』さんからご寄稿いただきました。
-以上-
今回は『マンガのレビュー・情報サイト ネルヤ』さんからご寄稿いただきました。
■Amazon売り切れ、“難民”発生。でも重版なし――“余ってる”のに品薄になる
マンガの流通ジレンマ
マンガや書籍は店頭にない場合、書店から注文することができる。これは昔からある
方法なので利用したことがある人も多いだろうが、ご存知のとおりすべての作品が必ず
手に入るわけではない。
22日、こうしたマンガの流通と在庫をめぐる問題がTwitterの書店員やマンガクラスタの
間で話題になった。
■TLで話題に上がった「市中在庫」とは何か?
書店で注文しても入荷できないというとき、いくつかのパターンが考えられる。代表的な
のは、いわゆる「絶版(=品切れ重版未定)」。出版社にもすでに在庫がなく、かと
いって重版する(新たに作品を作る)予定もないので手に入らないというケースだ。
だが、商品はあるのに手に入らないということもある。たとえば、「市中在庫」が多すぎ
る場合だ。
「市中在庫」というのは、書店にある在庫のこと。日本の場合、一般的に本が店頭に並ぶ
とき、出版社から委託販売されている形になり、売れなかった場合は(さまざまなルール
はあるが)原則として出版社に返品できる。つまり、出版社から見れば、店頭に並んで
いる作品でも、売れていなければ在庫と同じなのだ。
そのため、一部の書店で売り切れていても、大型書店などに大量に単行本が残っている
(市中在庫が多い)場合、注文が入っても重版を行わず、書店からの返本を待って再配本
というケースは実際多い。だが、その結果、読者が読みたいときに作品が届かないことは
起きてしまう。
また、TLでは「出版社にはあるが、取次(本の流通業者)に在庫がないというパターン」
も挙げられていた。出版社は印刷した本を、すべてひとつの取次に渡しているわけでは
ない。複数ある取次サイドはそれぞれに預かる本の数を決めており、ある取次には在庫が
あって、別の取次には在庫がないということもありうる。また、出版社に在庫があっても
、取次が持っていないこともある。
書店は取次だけでなく、出版社に直接注文をすることももちろんできる。だが、出版社に
よって追加注文のシステムもさまざまで煩雑であるため、書店によっては取次とのみ
やりとりをしている店舗もあるようだ。こういった店舗の場合、出版社に在庫があっても
「入荷なし」となる場合があるだろう。
ソース:ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/248066
(つづく)
2 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[sage] 投稿日:2012/09/09(日) 04:42:25.07 ID:???
>>1のつづき
■Amazonでは売り切れ、でも実売は……
こうした流通のミスマッチ問題は、しばしば話題になることがあり、場合によっては
流通システムや出版社、取次への批判に直結することも多い。「取次の配本がバカだから
」「出版社がいつまでも重版しないから」といった論だ。
こうした批判はある面では間違ってはいない。出版社は読んで欲しいと思っており、
読者は読みたいと思っているのに、商品が届かない。これは小売業にとってもっとも
不幸な状態であり、本来であれば絶対に避けたいことだ。
出版社や取次は基本的に「見つからない!」という声に対して謝るしかない。だから、
いっそう読者や作家からすれば怠慢に見えてしまう。だが、彼ら自身も届けられない
ジレンマに苦しんでいる。
たとえば、市中在庫の問題。出版社の人間に聞くと、こんなケースがよく起こっているという。
100冊の本があったとして、それを大型書店に50冊、中小規模書店に2冊ずつ合計25店舗に
分配。結果、大型店では50冊中20冊、半数の小規模店で売り切れ、残り12店舗で各1冊売れた。
これは一見悪くない数字だ。売り切れている店舗も多いので、そのエリアの読者は「
足りない」と感じるし、書店からの追加注文も入る可能性は高い。しかし、計算してみる
と、実売率は「20+26+12」でわずか58%。4割以上が“余っている”状態だ。
発売直後の動きならともかく、ある程度の期間をかけてこの数字なら、出版社としては
重版できないのが実情だという。もちろん、リスクを冒して重版することで、店頭で
火が付き、ヒットにつながる可能性もあるだろう。だが、ますます在庫が増え、重版する
ことで赤字になっていく可能性の方が高い。かといって、市中在庫がすぐ返ってくるわけ
でもないので、エリアによっては品薄感が続くし、中小書店の売りたいのに売れないと
いう不満も高まる。出版社にとって返本はイヤなものだが、市中在庫が偏っているとき
などは「むしろ返本してほしい」と思っていることもあるようだ。
これはAmazonなどでも同じ。「Amazonで売り切れが続いている」という場合も、実は
実売30%程度なんてこともあり得るという。毛細血管のように張り巡らされた書籍の
流通は、一部だけ見てもそれが全体像と一致するとは限らないわけだ。
さらに、意外と論点として挙げられないが、返品、再配本のコストもバカにならないと
いう。再流通させるコストだけでなく、「改装費」もある。何度も店頭に並び、流通を
繰り返せば新品の本も傷んでくる。これをキレイにし、カバーを掛け替えたりするのが
本の改装。ケースバイケースだが、こうした再配本を3回も行うと利益がなくなるという
出版社もあるという。
(つづく)
3 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[sage] 投稿日:2012/09/09(日) 04:43:19.36 ID:???
>>2のつづき
■商品であり、販促ツールでもある本
なら、もっと均等に近くなるように配ればいいとも思えるが、なかなかそうもいかない。
本という商品は、たぶんちょっと特殊なものだからだ。
たとえば、洗剤やお菓子であれば、店頭以外のメディアで大々的な広告を打つモデルが
一般的だ。が、刊行点数(商品の種類)が多い出版では、そういうモデルはほとんど
なく、多くの人が店頭でその存在を知る。つまり、本は商品であると同時に、それ自体が
販促物に近い側面も持っているのだ。
均等に近い配本にして、数冊程度ずつ入荷しても、書店で大きなスペースは確保できない
。1冊や2冊だと、最初から棚刺し(表紙を見せるように置く平積みでなく、本棚にささっ
て背表紙しか見えない状態)になってしまい、ほとんど目に止まらない状態になる。
こうなると1冊入って1冊残るというパターンが多くなる。その店舗では実売0%だ。2冊
入った書店で1冊売れても50%、3冊入って2冊売れてようやく60%オーバー。
一般に本を全国の書店に行き渡らせるには1万部前後必要になるといわれている。最初
から数十万部、数百万部と印刷されるヒット作はいいが、多くの作品はそんなに刷られる
ことはない。少部数の作品になれば、初版数千部というのもザラだ。そもそもすべての
書店に1冊ずつ配ることもできないわけだ。この状態で少部数ずつ配本するのはむしろ
自殺行為に近い。結果、一部の書店に本が集中し、「あるのに手に入らない」市中在庫
問題が起こったりする。
■“難民”になったらどうすればいい?
では、我々読者がきちんと欲しい作品にリーチするにはどうすればいいだろう?
流通システムの改善というのはもちろん課題としてあり、たとえばどこに何冊あるかが
いつでもわかるデータベースを作るというような案が出されることがある。が、現実問題
として街の本屋さんから大手チェーンまでを横断するシステムを一括で導入するのは、
なかなか難しい部分がある。配本数の最適化も何十年と試行錯誤を繰り返しながら進んで
きたのが今の状態で、今後も少しずつ変わっていくしかないだろう。
読者ができることとして一番確実な方法のひとつは予約だ。欲しい本は事前に書店で
予約して、確保しておく。
とはいえ、いつどんな作品が出るかを詳しく把握している人はそう多くないだろう。
発売日以後であれば、書店の在庫検索を使うのも手っ取り早い。ジュンク堂や紀伊國屋
書店など、オンラインである程度の在庫状況を知ることができる書店もある。
近隣にそういった書店がない場合は、e-hon*1を使う手もある。これは取次のトーハンが
運営しているサイトで、注文すると近くの書店に本が届き、受け取ることができるという
もので、いわば、書店での注文を自分でできるサービスだ。在庫さえあれば2日以内に
出荷され、書店で受け取るなら配送料もゼロ。利用している書店で注文ができないときは
、こちらで在庫を探してみるのも手だ。
(つづく)
4 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[sage] 投稿日:2012/09/09(日) 04:44:10.18 ID:???
>>3のつづき
*1:e-hon
http://www.e-hon.ne.jp/bec/EB/Top
マンガ、書籍の流通は複雑で難しく、著者、出版社、取次、読者などの間で批判や対立が
起こることも多い。仕組みの抱えるジレンマを理解することで、全体が協力して改善に
向かうこともできるのではないだろうか。
【08/23追記】
取次が運営しているサイトとして、ほかに日販のHonyaClub*2というサイトがあるという
情報をいただきました。
直販、書店への取り寄せ、 在庫確認などができるようですので、参考までに追記させて
いただきます。
*2:HonyaClub
http://www.honyaclub.com/shop/default.aspx
執筆: この記事は『マンガのレビュー・情報サイト ネルヤ』さんからご寄稿いただきました。
-以上-
池袋のジュンク堂が「SFの殿堂」に!夢枕さん「SFの裾野は広い」山田さん「若い世代が読むきっかけになれば」
1 名前:おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★[] 投稿日:2012/10/08(月) 08:52:26.76 ID:???0
約1千点、3千冊のSF小説やマンガ、批評などを集め、販売する
「SFブックミュージアム」が10月6日、東京・池袋のジュンク堂書店で始まった。
来年50周年を迎える日本SF作家クラブの記念イベントで、6日には元会長の
夢枕獏さんと山田正紀さんによるテープカットもあった。
会場は「日本SF巨匠の部屋」「海外SFスタンダード」
「サブカルSFの標本」「SFコミック往年の名作」などテーマごとに陳列され、
オンデマンド出版のため書店ではほとんど見られない『小松左京全集完全版』(城西国際大学出版会)や『しずおかSF 異次元への扉』
など地方の出版物も並べられている。
夢枕さんは「これだけSF関連本が集まると壮観です。まだ読んでいなかった名作もあって、
改めてSFのすそ野の広さを感じました」と話した。山田さんは
「若い世代がSFを読むきっかけになって欲しい」と話した。
http://book.asahi.com/booknews/update/2012100400008.html
約1千点、3千冊のSF小説やマンガ、批評などを集め、販売する
「SFブックミュージアム」が10月6日、東京・池袋のジュンク堂書店で始まった。
来年50周年を迎える日本SF作家クラブの記念イベントで、6日には元会長の
夢枕獏さんと山田正紀さんによるテープカットもあった。
会場は「日本SF巨匠の部屋」「海外SFスタンダード」
「サブカルSFの標本」「SFコミック往年の名作」などテーマごとに陳列され、
オンデマンド出版のため書店ではほとんど見られない『小松左京全集完全版』(城西国際大学出版会)や『しずおかSF 異次元への扉』
など地方の出版物も並べられている。
夢枕さんは「これだけSF関連本が集まると壮観です。まだ読んでいなかった名作もあって、
改めてSFのすそ野の広さを感じました」と話した。山田さんは
「若い世代がSFを読むきっかけになって欲しい」と話した。
http://book.asahi.com/booknews/update/2012100400008.html
バイトの「レシートご入用ですか?」の問いに対してクレームが入った
932 名前:無名草子さん[sage] 投稿日:2012/09/09(日) 23:19:30.75
バイトの「レシートご入用ですか?」の問いに対してクレームが入った
「レシートは渡して当然なんだから聞くのはおかしくないか!」ってキレられた
「当然レシートはお渡しするべきだと思っています。レシートが不要な方もいらっしゃい
ますから確認の為に聞いたんだと思います。」と答えたんですが怒りが収まらず
「この店は不正をしているんじゃないか!税務署に報告する!」と言われました。
真面目にやってきたのに不正者扱いされるなんて・・・
とりあえず今後は余計なことは言わずにレシートをお渡しするように指導した。
皆さんもお気をつけください。
バイトの「レシートご入用ですか?」の問いに対してクレームが入った
「レシートは渡して当然なんだから聞くのはおかしくないか!」ってキレられた
「当然レシートはお渡しするべきだと思っています。レシートが不要な方もいらっしゃい
ますから確認の為に聞いたんだと思います。」と答えたんですが怒りが収まらず
「この店は不正をしているんじゃないか!税務署に報告する!」と言われました。
真面目にやってきたのに不正者扱いされるなんて・・・
とりあえず今後は余計なことは言わずにレシートをお渡しするように指導した。
皆さんもお気をつけください。
復刻マンガをネットだけでなくリアル書店でも ネット会社が渋谷に開店
1 名前:ベガスρ ★[] 投稿日:2012/10/05(金) 14:10:38.09 ID:???0
”復刻マンガ、書店でも ネット会社が渋谷に開店”
一度は絶版になりながらファンの後押しで復刻されたマンガを集めた「渋谷サブカル書店」が、
東京・渋谷の渋谷パルコパート1にオープンした。ネット上で復刻の要望を募る出版社、
復刊ドットコムが初めて開いた「リアル書店」だ。
店内には「のらくろ喫茶店」(田河水泡作)、「サイボーグ009」(石ノ森章太郎作)など
約300タイトルが並ぶ。9月刊行開始の「ブラック・ジャック大全集」(手塚治虫作)は、
「週刊少年チャンピオン」連載当時のB5判サイズを初めて再現した単行本だ。
復刊ドットコムはサイト上で100票以上の要望が集まった本について、版元と交渉して
約5千点を復刊した。復刊が困難な場合は自社が新たな版元となり約800点を復刻、
ネットなどで販売してきた。
リアル書店について、同社の岩本利明・営業部マネージャーは「ネットでは、はじめから欲しかった本を
ピンポイントで購入する。知らなかった復刻本と出会ってもらえるのは実店舗ならでは」と狙いを話す。
渋谷パルコパート1は9月、土地柄多い外国人客も意識して、6階フロアを
日本のポップカルチャーを前面に出してリニューアルした。
岩本マネージャーは「海外から来る若いマンガファンにとって、のらくろや手塚作品など
『マンガの古典』を初めて手に取る機会になれば」。
(上原佳久)
画像
復刊されたマンガが並ぶ店内=東京・渋谷の渋谷パルコパート1
http://book.asahi.com/S2800/upload/2012100300011_1.jpg
ブック・アサヒ・コム
http://book.asahi.com/booknews/update/2012100300011.html
”復刻マンガ、書店でも ネット会社が渋谷に開店”
一度は絶版になりながらファンの後押しで復刻されたマンガを集めた「渋谷サブカル書店」が、
東京・渋谷の渋谷パルコパート1にオープンした。ネット上で復刻の要望を募る出版社、
復刊ドットコムが初めて開いた「リアル書店」だ。
店内には「のらくろ喫茶店」(田河水泡作)、「サイボーグ009」(石ノ森章太郎作)など
約300タイトルが並ぶ。9月刊行開始の「ブラック・ジャック大全集」(手塚治虫作)は、
「週刊少年チャンピオン」連載当時のB5判サイズを初めて再現した単行本だ。
復刊ドットコムはサイト上で100票以上の要望が集まった本について、版元と交渉して
約5千点を復刊した。復刊が困難な場合は自社が新たな版元となり約800点を復刻、
ネットなどで販売してきた。
リアル書店について、同社の岩本利明・営業部マネージャーは「ネットでは、はじめから欲しかった本を
ピンポイントで購入する。知らなかった復刻本と出会ってもらえるのは実店舗ならでは」と狙いを話す。
渋谷パルコパート1は9月、土地柄多い外国人客も意識して、6階フロアを
日本のポップカルチャーを前面に出してリニューアルした。
岩本マネージャーは「海外から来る若いマンガファンにとって、のらくろや手塚作品など
『マンガの古典』を初めて手に取る機会になれば」。
(上原佳久)
画像
復刊されたマンガが並ぶ店内=東京・渋谷の渋谷パルコパート1
http://book.asahi.com/S2800/upload/2012100300011_1.jpg
ブック・アサヒ・コム
http://book.asahi.com/booknews/update/2012100300011.html
最新記事
カテゴリ
人気商品ランキング
アクセスランキング
中野梓
スポンサードリンク
月別アーカイブ
- 2014/11 (1)
- 2014/10 (1)
- 2014/07 (1)
- 2014/06 (2)
- 2014/05 (4)
- 2014/04 (9)
- 2014/03 (1)
- 2014/02 (2)
- 2014/01 (27)
- 2013/12 (60)
- 2013/11 (67)
- 2013/10 (248)
- 2013/09 (240)
- 2013/08 (248)
- 2013/07 (248)
- 2013/06 (173)
- 2013/05 (239)
- 2013/04 (240)
- 2013/03 (217)
- 2013/02 (92)
- 2013/01 (144)
- 2012/12 (183)
- 2012/11 (195)
- 2012/10 (188)
- 2012/09 (181)
- 2012/08 (217)
- 2012/07 (213)
- 2012/06 (210)
- 2012/05 (216)
- 2012/04 (181)
- 2012/03 (64)
- 2012/02 (183)
- 2012/01 (155)
- 2011/12 (152)
- 2011/11 (141)
- 2011/10 (123)
- 2011/09 (111)
- 2011/08 (120)
- 2011/07 (100)
- 2011/06 (113)
- 2011/05 (122)
- 2011/04 (120)
- 2011/03 (106)
- 2011/02 (111)
- 2011/01 (105)
- 2010/12 (108)
- 2010/11 (125)
- 2010/10 (96)
- 2010/09 (43)
- 2010/08 (32)
- 2010/07 (27)
- 2010/06 (14)
- 2000/01 (1)
最新コメント
- Nom:ビジネス書をドヤ顔で読んでるリーマンみると悲しくなってくるよね・・・ (04/22)
- 名無しの読書家:ロリババアっていうのか長生きだけど見た目少女で口調は「~じゃ」とかいう感じのキャラ (11/27)
- 이연:円城塔さんの『Self-Reference ENGINE』が米国の文学賞「フィリップ・K・ディック賞」の候補作に (11/26)
- Thomassi:芥川賞作家・黒田夏子が本名を明かさない理由 (11/26)
- ClaudioMn:芥川賞作家・黒田夏子が本名を明かさない理由 (11/24)
- www.7hhk.com:「小説家になろう」とかいうサイトが面白すぎるwwwwww (11/20)
- DanielMa:芥川賞作家・黒田夏子が本名を明かさない理由 (11/16)
リンク
- LogPo!2ch
- 2chnavi
- まとめちゃんねる
- 他力本願
- ブーンあんてな⊂二二二( ^ω^)二⊃
- ハジマタあんてな\(^o^)/
- 2ブロネット
- にゃんてな!
- 2chあんてな九十九尾
- アンテナシェア
- ついてな
- ('A`)あんてな
- 楽々アンテナ(∪^ω^)
- 楽々アンテナV2
- ほむ速
- しぃアンテナ(*゚ー゚)
- まとめようず
- とろたまヘッドライン
- MatomeJa 2chまとめあんてな
- アンテナ速報
- 記事しま.com
- ねとしん(インターネット新聞)
- てんぷアンテナ
- まとめアンテナ!!
- エスノあんてなGT
- もしもしアンテナEX(゚ω゚)
- Girinio.jp (ギリニオ.jp)
- ぐるぐるログ
- おまとめ
- 2chまとめブログのアンテナ
- ふぁびょんアンテナ
- 棒読みあんてな(2ch)
- 2chまとめインデックス
- アナグロあんてな
- 紳士協定 - 2chまとめ
- アテナあんてな
- 2chまとめブログ集
- Rotco
- まとめアンテナZ
- 2chアンテナしんぶん
- 2ch log cache
- カリモフ
- あるみら!
- ワロタあんてな
- Fast2ch
- ログ・ツーデー
- テレビよりアンテナ
- マトメナ
- アンテナch
- だめぽアンテナ
- オワタあんてな
- j-antenna
- やる夫アンテナ(べーた)
- ショボンあんてな(´・ω・`)
- 2ちゃんマップ
- シャキンあんてな(`・ω・´)
- アニポ
- とりのまるやき
- やる夫.jp
- 不思議.net
- ぱんだとらんすれーたー
- 2してん!
- かがくのじかん
- ハムスター速報
- SS 森きのこ!
- SS徒歩5分
- 【2ch】ニュー速クオリティ
- アルファルファモザイク
- 暇人\(^o^)/速報
- 【2ch】ニュー速VIPブログ(`・ω・´)
- 何でもありんす
- ニュー投
- カナ速
- ニュース2ちゃんねる
- もみあげチャ~シュ~
- VIPPERな俺
- ワラノート
- ニコニコVIP2ch
- 廃人にゅーす@2ちゃんねる
- ときどき速報
- ニュー速証券
- お絵かき初心者の学習部屋
- 2ちゃんねるアーカイブ
- やる夫と学ぶ就職活動
- 最新の情報に更新
- Chicken-Skin
- 読書と2chと感想と
- まとめまみれ ちゃんねる♪
- くいもんニュース
- 掃除からはじめる家事手伝い
- 奇妙奇天烈スタイル
- オタクニュース
- ニコニコ動画まとめ FPS
- 海外ちゃんねる
- こじきちゃんねる
- 私立ギコ猫学園
- 話題の道標
- スマホNavi
- ダンパ速報
- おすすめ・比較の2chまとめ
- ドゥ・ミゼラブル速報
- 俺のNEWS
- サイキョー遊戯王
- マネーニュース2ch
- 2ch的スポーツニュース速報
- わた速/SS速報VIP・SS まとめブログ
- ひとよにちゃんねる
- かがくのちからってすげー!速報
- 将棋速報FUZIP
- モテたがり症候群
- 2ちゃん わらふく
- むくり速報
- 電網観察記
- すっぴんですか?
- アクア水槽館
- ニューソクロペディア
- モレ速
- まっ、テキトーに
- 気になったニュース(`・ω・´)
- 教えろください
- ★新文章表現速報@VIP★
- 適当にネット小説をまとめる速報
- 気になるたけのこ速報VIP
- 既出上等
- 2ch旅紀行
- となりの芝生はどんな色?
- 競馬ニュース速報【うま速】
- 2ch Hokkoly
- mjsk速報
- ぷち@ソース
- ノムケン!!
- 来世から本気出す
- まとめっちゃれら速報
- 嫁と姑 鬼女ブログ(`・ω・´)
- 2chって(´・ω・`)何ですか?
- 2chの映画レビュー評価
- 痛い相談
- 韓流速報<丶`∀´>
- パチスロ頑張っていきまっしょーい
- ごろりんこ
- Chemience
- ごはんはおかずだよ
- はーとログ
- まとめるよ
- 自由気ままなログ倉庫
- しお韓、半万年の歴史
- 良い子のブログ
- 麻呂の部屋管理人
- 隣人注意報
- ニコライフ
- ザ・面白動画!
- ロムちゃんねる
- コミちゃんねる
- NEWS PICK UP
- にゅーすAtoZ
- ひまねっと
- にゅーすなう!
- SSC-NEWS
- 【2ch】PICK UPニュース!
- シャルロッ党
- 移譲記章
- ねたたま!
- 変人窟
- カレーにつけるパンってナンだっけ?
- New discovery
- ほっとにゅーすにちゃん
- くまくまニュース
- サバンナニュース2ch
- 面白ニュース
- ゆるなり速報
- 魔天
- TAB3
- 世界オモシロ探検隊あゆーにゃ
- ラシネスカルチャーストリート
- 聖エルザクルセイダーズFANブログ
- 人気ライトノベルまとめ!
- (≧∇≦)個人的なネット小説リンク所
- 小説が書けない.com
- 管理画面
メールフォーム
FC2カウンター